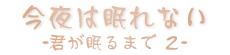 2001.6.17 ・◆・ A-Oku
「オスカーさま」 聖殿の廊下を歩く彼の背後からひとつの声が追いかけてくる。 その声の持ち主が誰であるのかはオスカーにはすぐにわかった。だがどんな反応するのか見てみたくてわざと気づかないふりをするした。 「オスカーさまっ、気づいてらしているのでしょう?」 腕をつかまれ、ようやくオスカーは振りかえった。 そこにはいるのはよく知った金の髪の女性。最愛のひと、アンジェリークである。 「どうした?」 これは赤信号かな。 アンジェリークを見てオスカーは思う。 自分に対する呼びかけが『オスカー』から『オスカーさま』になっている。 本人は気づいていないようだがアンジェリークは怒ると口調が女王候補だった頃に戻ってしまう。 アンジェリークの素直な感情表現はオスカーにしてみれば、時にかわいらしく、時にはまぶしささえ感じられる。今もつい口元に浮かびそうになる笑みを押しころし、あくまで何気なさを装ってオスカーは尋ねていた。 対するアンジェリークはと言えば、いつもと様子が違う。周囲を伺うようにみまわした。 「ここでは、ちょっと...。わたしの部屋に行きましょう。」 どうやら人目を気にする話題らしい。 オスカーはアンジェリークに手をつながれ、引っぱられるように連れて行かれた。 アンジェリークは部屋の鍵を取り出した。驚くにはあたらない。 彼女は普段、ここよりもに女王陛下そのひとの執務室にいることが多い。 オスカーはここには二人のほか誰もいないという事実をよく覚えておくことにした。 部屋についたものの、アンジェリークは口を開きかけては止める、という動作を2度ほど繰り返した。 何か言いたくない話題なのだろう、と踏んだオスカーはアンジェリークが話しやすくするために水を向けた。 「それでどんな話なんだ?」 それでもアンジェリークはためらいを見せ、やがておずおずと、だがはっきりした声で目の前にいる人物に問いかけた。 「今日ジュリアスさまに何をおっしゃられたんですか?」 「ジュリアス様?」 アンジェリークはうなずいた。彼女の話はこうだった。 先ほど陛下の言を伝えるべく光の守護聖をもとを訪れたアンジェリークだったのだが、帰る間際にこう言われたという。 「そなたとオスカーがどのような生活をしようと立ち入るつもりはないのだが。」 「はい。」 「執務に差し障りのあるようなことでは困るのだ。」 「え?」 「いや、すまぬ。余計なことを言った。忘れてもらいたい。」 考えてみてもアンジェリークに思い当たる節はなかった。となればオスカーが何かを言うなりするなりしたに違いない。彼女はそう考えたのだ。 「ああ。」 オスカーは両腕を組んだまま話を聞いていたが得心がいったように肯いた。 ジュリアスさまが彼女にそんな話をするとは予想外のことだったが。 理由を求める彼女の目を見つめてオスカーは穏やかに話した。 「昨夜俺が仕事を家まで持って帰ってきてしまったことは知っているよな?」 アンジェリークは首を縦にふった。そのせいで自分が夜半までひとりきりで過ごしていたことは記憶に新しい。 「それは朝一番にジュリアス様に提出するはずだったんだが…完成しなかった。」 必ず朝一番で提出します、と昨日オスカーはジュリアスに約した。 だから今朝ジュリアスの執務室へおもむいて、提出できない旨を伝えていた。 その理由をジュリアスに聞かれた時、オスカーはこう答えた。 「アンジェリークが離してくれなかったので」と。 「なっ…」 アンジェリークは言葉が続かなかった。 オスカーの答えでジュリアスに何を言われたのかがわかったから。 はげしく高鳴る動悸を押さえてアンジェリークはようやく言葉を口にした。 「どうしてそんなことを? それじゃジュリアスさまが誤解されたのは無理もありません。ううん、それならなぜ最初から最後まで話をして下さらないんですか。」 「君が泣いていたところから?」 アンジェリークの目に飛び込んできたのは静かな瞳だった。 胸を、うたれた ゆうべは激しく窓を打つ雨の音が眠りを破った。 雷の音に震えていた。 暗い空を切り裂く光がこわかった。 ひとりで眠るのがこわかった。 そんな自分の抱きしめてくれたオスカーの腕の中は暖かくて、彼の心臓の鼓動を聞いているうちにいつの間にか眠ってしまっていた。 目覚めたときも変わらずオスカーはそこにいて。 「昨夜はよく眠れたか?」 そう言っておはようのキスをしてくれた。 オスカーは自分を思いやってくれたのだろうか。 アンジェリークは何かを言おうと思ったのだけれども言葉が見つからなかった。 それでも何か言おうとして出てきたのはこんなことだった。 「でも、顔から火が出るかと思ったんだから。」 「まあ…炎の守護聖といるんだからそれには慣れてもらわないと。」 にやにやにや。 そんな感じで笑うオスカーにアンジェリークは腹が立った。 「もうっいいです。ありがとうございました。」 オスカーを押し出すように両手を出したところで、逆に手を捕まれてしまった。 「もう終わりか?」 「そうですっ。はなしてください。」 「つれないな。俺はこんなに君と一緒にいたくて仕方ないのに。」 オスカーの腕がさりげなくアンジェリークの腰にまわされた。 「誰もいないんだったな。」 危険な赤い色が近づいて来るのを感じてアンジェリークは声をあげた。 「だめ。だめったら絶対だめっ。ここは神聖な女王補佐官の執務室なんですからね。そんなことはダメです。」 そんなこと、の意味を分かっているのかいないのかアンジェリークは首をぶんぶん横にふった。 オスカーを押し返そうと腕がもがいている。 本気を出せば彼女が腕の中に閉じこめることなど可能だろうに意外にもオスカーは引きさがった。 くまのぬいぐるみを視界の端におさめながらオスカーは肯いた。 「そうだな。今は時間がなさそうだ。少なくとも2時間はないと。」 「に、2時間?」 動揺するアンジェリークを見やってまたにやにや笑いを浮かべた。 「3時間あればもっといい。」 また後で、と声をかけて部屋を出ていったオスカーにも気づかない様子でアンジェリークは手近にあったソファー座り込んだ。 「どうしよう....」 昨夜は外でだったが今夜は内側で雷が鳴ることになりそうだ。 やっぱり今夜も眠れそうになかった。 |