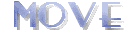 2002.4.15 ・◆・大庭美樹
「オスカーさまー!」
明るく弾けるような声に呼ばれて振り返ると、アンジェリークが転げるようにして走ってくるところだった。
相変わらず、本当に転がってしまいやしないかとつい心配になるような走り方だ。王立研究院からの帰りらしく、両腕に資料のファイルをしっかりと抱え込んでおり、あのまま転んだら到底無傷では済むまいとはらはらさせられる。
「おいお嬢ちゃん、あんまり慌てて転ぶなよ!」
思わずそう声を張り、自分の方からも足早に近付いてやると、アンジェリークは肩で息をしながら瞳をきらめかせてオスカーを軽く睨んだ。
「また子供扱いして。大丈夫ですよ、これでも私、バランス感覚はいいんですから」
とてもそうは思えないがと密かに思いながらも、まだ──幸いにも──転んだ現場に出くわしたことがないのは事実だったので、「それでも気をつけてくれよ」と言いながらくしゃくしゃと頭を撫でてやるに留めておいた。
アンジェリークは、ちらっと更に怒ろうかどうしようか迷うような風情を見せたが、結局は小さく「もう」と呟きながらも大人しく彼に頭を撫でさせて、その口元に微かにはにかんだような笑みすら浮かべた。
……結構な進歩じゃないか。
たったそれだけのことで喜びに胸が小さく躍るあたり、自分も相当参っているなと苦笑が漏れる。
だいたい、なんだってこんなお嬢ちゃんに惹かれてしまったものか。お子さまは守備範囲外だった筈なんだがなあとしみじみ思いながら、オスカーはアンジェリークのふわふわの髪の感触を楽しむようにぽんぽんと軽く撫で、名残惜しくはあったが彼女が妙に意識をし始める前にそっと手を引いた。──この辺の見極めに気を遣うというのは、彼にとってはちょっと新鮮な感覚だった。
「プレイボーイ」などとあだ名され、世間で言われているほど手当り次第だった訳でもないが、それなりに刹那の恋を渡り歩いてきたオスカーである。いつも、自分が対等以上と認めた相手との誘惑したりされたりの駆け引きを、随分と楽しんできたものだ。
だがこのお嬢ちゃん相手のこれは、「恋のかけひき」以前の問題だ。第一、下手な動きをした途端にぱっと跳ね上がって逃げてしまいそうな危うさもあって、慎重の上にも慎重を期さねばならない。
もっとも、そろそろ次の一手に出てもいいだろうかと思えるときもあるのだが、なかなか確信には至れずにいる。時として、それはいかにももどかしい。もどかしいのだが、アンジェリークが相手であればそれもまた楽しいような気にもなるのだから手に負えない。
(惚れた弱味とはよく言ったぜ)
内心で肩をすくめると、オスカーは片手を腰にあて、もう一方の手で前髪を軽くかきあげながらアンジェリークを見下ろした。
「で? 俺に何か用かな、お嬢ちゃん?」
軽く笑って問いかけると、途端にアンジェリークの顔がパッと明るくなった。いつもながら、表情の変化が実に鮮やかで、一瞬も目が離せないような気にさせられる。
「あのね、エリューシオンの発展が、フェリシアを上回ったんです!」
大きな瞳にキラキラと嬉しそうな誇らしげな光をたたえて、アンジェリークは高らかに宣言した。
「ほう、そりゃすごい。やったな、お嬢ちゃん」
オスカーの賞賛に、アンジェリークは嬉しげに頬を染めてはいっと大きく頷いた。
「オスカーさまに、一番にご報告したかったんです。嬉しい!」
「俺に?」
素直に嬉しく感じると共に何か意外なような気もして、オスカーは思わず問い返した。アンジェリークは彼の眼を見ながらしっかり頷いて、それからふわっと柔らかな微笑みを浮かべた。
「はい。だって、エリューシオンに最初に建ったのはオスカーさまを讃える神殿だったし、それに今回も、オスカーさまのお力が大陸を力強く導いてくれたおかげですから」
一瞬、女神の翼をその背の上に見て、オスカーは目を瞬かせた。微かな痛みが、胸の奥にツキリと走る。
だが彼は、すぐに何食わぬ顔になって、彼女ににこりと微笑みかけた。
「そいつは光栄だ。だが、俺はお嬢ちゃんの依頼に応じてサクリアを送っただけだからな。俺の力と言うよりは、お嬢ちゃんの力だろう」
「それでも、オスカーさまのおかげです」
アンジェリークはにこにことオスカーを見上げて続けた。
「パスハさんもね、エリューシオンが炎の力を一番効率良く吸収して呼応しているようだって。私、嬉しいんです。私の大陸が、炎の力に一番強く反応してくれて。だってそれは、エリューシオンが強い生命力を持っている証拠でしょう?」
アンジェリークは、ふふっと小さく首をすくめて笑った。
「私、最初に随分いろいろ失敗して、大陸の民には迷惑をかけているから。それでも強く生きてくれてありがとうって、エリューシオンにそう言いたい気持ちなんです。その力を与えて、導いてくれたのはオスカーさまですから。だから、最初にお礼を言いたかったの」
そう言ってまっすぐ見上げてくる彼女の表情からは日頃の子供っぽさは影をひそめ、どこか凛と張った気高さすら感じられた。
エリューシオンを語るとき、アンジェリークの背筋は誇らしく伸び、その瞳には愛が宿る。それはひどく美しく彼の目に映り──オスカーは我知らず手を伸ばして、彼女の頬にそっと触れた。
「それは多分、君自身の資質だ。最初は頼りなくも見えたが、本質はしなやかに強い。…きっと、君はいい女王になるだろう」
その声に含まれた厳粛な敬意を感じ取ってか、アンジェリークは少し頬を染めながらも神妙に彼を見上げて、それから嬉しそうな笑みを浮かべた。
オスカーはすっと身をかがめると、微笑みを乗せたその唇の上にごく軽く自分の唇を掠めさせた。
彼女は一瞬、何が起こったのかわからなかったような表情を浮かべ、次の瞬間一気にボッと耳まで真っ赤に染まった。
「エリューシオンと、それから君に、炎の守護聖の祝福を」
オスカーはそう言いながら指先で素早く彼女の唇を撫で、もっとその甘美な柔らかさを味わいたがる気持ちを無理矢理ねじ伏せて身を起こした。
アンジェリークは、どう反応していいのか戸惑うようにオスカーを見上げ、彼の視線に出会うと一層赤くなってうつむいてしまった。
と、そう見えたのは、ほんの一時だった。アンジェリークは唇をきゅっと引き締めると、再びさっと頭をもたげ、強い瞳で挑戦的に彼を見返してきた。
「オスカーさまの『祝福』って、強引」
非難に近いその抗議の声に、オスカーは半ば虚を突かれ、半ばは心の浮き立つような手応えに深い喜びが湧き上がってくるのを感じた。
そうだ、この瞳だ。
ふつふつと湧いてくる張り詰めた喜びの中で、オスカーは満足げに目を細めた。
いつも素直で自然な感情の発露のままに、いつの間にか彼の懐深く飛び込んできて、そして不意打ちのように、この煌めく強い瞳で心ごと貫いてゆく。この自分を相手に一歩も引かない、そんな彼女だから惹かれたのだと、彼は心の奥にかみしめるように思った。
突如として、この緑の炎を自分だけのものにしたいという圧倒的な思いが突き上げてきた。どうしてもどうしても彼女が欲しい。何を犠牲にしてもいい。ついさっきまで、彼女が女王になるなら手を引くこともやむなしと思っていたのが嘘のようだった。
だが不思議と、だったら試験を放棄させようというような気にはならなかった。
例え彼女が女王の地位についたとしても、一人の女としてのその愛を勝ち取ってみせる。その挑戦は、胸の炎をいやが上にもかき立てた。
…ライバルは宇宙そのものか。相手に取って不足はない。
オスカーはニッと不敵に笑うと、揺るがない視線で見つめてくるアンジェリークに向かって、軽く眉を上げてみせた。
「強引かな?」
「強引ですよ。同意もなしに、女の子にキスしちゃうなんて。……ファーストキスだったのに」
最後の一言を、口の中で付け足すようにちょっと恨めしげに呟く様子が愛らしく、オスカーは一層笑みを深めた。まだたどたどしいことに違いはないが、彼女の方からも仕掛けてこようというならば、それに乗らない手はない。
「それなら、同意を求めたら、二度目のキスには応じてくれるのかな?」
「───!」
甘く問いかけた途端に再びばっと赤くなったアンジェリークの顎を軽く捉え、覗き込むようにして低く囁きかけた。
「俺としては、二度目はもとより、三度目も四度目もその後もずっと、君のキスを独占したいという気持ちがあるんだが」
からかっているわけではないと伝わるよう、瞳に力をこめる。
アンジェリークは頬を真っ赤に染めたまま、落ち着かなげにぱちぱちと瞬きした。その大きな瞳が、明らかな惑いと不信と微かな期待を宿して揺れる。オスカーの胸もまた、期待と不安にぎゅっと締め上げられた。
と、アンジェリークがふいっと拗ねたようにそっぽを向いた。
「ダメ」
短くてはっきりとした端的な答えに、オスカーはつい破顔した。否定の返事ではあるが、その声や表情には充分に脈がある。
自分の悪い癖だとは思うが、あまりあっさり手に入るよりこういう方が好ましい。彼女が初々しいなりにしっかりとした手応えを示してくれるのが嬉しかった。
「ダメなのか?」
一転、からかうように笑いながら覗き込んでやると、今度はむうっと睨んできた。
「…ダメです」
「どうして?」
「どうしても」
オスカーはクスクス笑って、降参の印に軽く両手を挙げた。
「じゃあ、今日は諦めよう。そのかわり、送るだけは送らせてくれよ」
そう言って、ファイルを持とうかと手を差し出す。アンジェリークは一瞬迷い、それからちょっと緊張ぎみに、抱えていたファイルを彼に手渡した。
その生真面目な表情に、ちゃんと対等のステージに上ってくる覚悟はあると見て、オスカーはゆっくりと微笑んだ。どうやら、次の段階へのゴーサインと受け取ってもよさそうだ。
「じゃあ行こうか、アンジェリーク」
まっすぐ見つめながら、意識して名前をはっきり発音してやると、彼女の眉がぴくんと跳ねてその頬に緊張が走った。
上出来だ。これからは口説くぞという暗黙のメッセージも、ちゃんと伝わったと見える。
…もっとも、彼の「本気」がどれほどのものか、彼女にわかっているとは思えないが。
なんにせよ楽しくなりそうだと、胸が躍る。
オスカーは会心の笑みを浮かべると、やや緊張ぎみなアンジェリークの背にごく軽く手を添えて、上機嫌で女王候補寮の方へと歩き出した。
・◆ FIN ◆・
BACK ・◆・ HOME
|