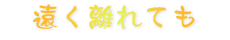
2001.4.11 ・◆・ 大庭美樹
ひとけのない夜の庭園を、彼はゆっくりと横切っていった。
淡い光の中に浮かび上がる噴水の前で足を止め、そして月明かりにきらめく飛沫を見上げて佇む。
せつない吐息が、その唇から漏れた。
──彼の恋する少女は、明日にも宇宙の女王となる。
最初からわかっていたことだ。
彼女は女王となることを望み、彼は黙ってそれを支えてきた。
力を送ることを依頼されれば誠意を尽してサクリアを注ぎ、依頼がなくとも必要と考えられる時には自ら進んで力を贈った。いつも真剣に彼女の相談に乗り、できる範囲で育成のアドバイスもしてきた。
いつか親友同士となっていたライバルに大差をつけて、勝利が確実となってからも、彼女は一切手を抜かない。その姿勢をこそ好ましいと思うから、支えてやりたいと心底思う。
力を送る必要がない時も、王立研究院に立ち寄って育成状況をチェックするのがいつの間にか日課になってしまった。その帰り道にこの噴水へと足が向くのもいつものことだ。それも、恐らくは今日で終わる。
これでいいのだと──よかったのだと、強がりではなくそう思う。
例え、恋しいものが手の中からすり抜けてゆく痛みに、心が激しく軋んでいても。
アンジェリーク。
……遠くへ、行ってしまうんだね。
彼は深く長い吐息と共に、噴水のほとりにゆっくりと腰を降ろした。
かつて、初めて愛しいと思った日、彼女がどこかはすっぱな仕種で腰掛けたその場所に。
人を恋する気持ちは、胸を揺さぶり息を詰まらせ、苦しいほどに心の全てを支配してしまう。なのに、そのきっかけとなるのは、なんてささいなことだったりするのだろう。
あれは、いつものように気持ちよく晴れた、日の曜日の午後だった。
特に約束していたわけでも、誘い合わせたわけでもなく、偶然庭園で顔を合わせたコレットと、なんとなくそのまま噴水の前で話し込んでいたときだ。
ふと、彼女の瞳が彼を通り越した背後へ向けられたかと思うと、一瞬せつなげに揺れた。
いつも元気に明るい少女のその表情につられて振り返ってみると、休みの日にもかかわらず正装姿の炎の守護聖が、こちらに気付いて足を止めたところだった。
「よう、今日も相変わらず可愛いな。ランディとデートか、お嬢ちゃん?」
「こ、こんにちは、オスカー様」
少し早口に挨拶し、ぺこりと頭を下げる少女に続いて彼も目礼すると、オスカーは屈託なく笑って頷き返してきた。
「こんな日の庭園は気分がいいな。充分に楽しんで、また明日から続く試験の英気を養うといい」
そう言うと、オスカーは彼等に向かって軽く手を上げ、鮮やかな笑みを残して宮殿の方角へと大股に歩み去って行った。
「日の曜日なのに、仕事なのかな」
つぶやいて傍らの少女を見ると、彼女はオスカーの後ろ姿をじっと目で追っていた。
日頃鈍い鈍いとゼフェルに馬鹿にされる彼ではあったが、この時はピンとくるものがあった。
「…もしかして、君、オスカー様のこと…」
少しためらいがちに問いかけたら、彼女は一瞬パッと頬を染めた。それから栗色の髪をさっと振り立てると、勝ち気な瞳をランディに据えて、どこか挑戦的に切り返してきた。
「そうですよ、いけませんか?」
「い、いや、いけないってことはないけど、でも──」
少しその勢いに押され気味になりながら、ランディは口籠った。
金の髪の現女王と炎の守護聖とが恋愛関係にあることは、長く聖地にいるものにとってはほぼ公然の事実だが、だからと言って軽々しく口にできる類いのことでもない。無用の混乱を避ける為、今回の女王試験の関係者には一応は伏せておくべきだろうとも、ジュリアスからは言われている。
それでもランディは、妹のようなこの少女が叶う見込みのない恋に突き進んでいくのは、できれば避けさせてやりたいと思った。
「言いにくいんだけど、その…オスカー様には、もう…」
心に決めたひとが、と続けようとしたところで、きらりと光る強い瞳にさえぎられた。
「知ってますよ、女王陛下でしょ」
早口にそう言い放って、コレットは噴水のほとりにストンとやや乱暴に腰掛けた。
「…知ってたのかい?」
驚いて問い返しながらその隣に腰を降ろすと、コレットはちょっと目を伏せながら、彼の方は見ずに言った。
「見てればわかりますよ、そのくらい。望みがないことだって、わかってます。──でもしょうがないじゃないですか。好きになっちゃったんだもん」
「アンジェリーク、君…」
とまどいながら言葉を探していたら、彼女はふと瞳を和らげて彼を見上げ、ふわりとした柔らかい笑みを浮かべた。その表情の劇的な変化に、ランディは思わずドキリとしてコレットを見つめた。
「心配しないで。ちゃんとあきらめられる自信はありますから。大丈夫、試験もきちんと続けられますよ。──私、アルフォンシアのこと、とっても愛していますもの」
初めて見るその大人びた笑顔の中に、ほんの少しのせつない寂しさと、強い誇りと深い愛とがないまぜになっていた。
「アルフォンシア」と発音する時にその海色の瞳に宿った優しい光を見た瞬間、ランディはずしりと体中に響くほどの衝撃を受けた心地がした。
多分、あの一瞬に、恋に落ちたのだと思う。
子供の頃に経験したような淡く幼い憧れはもとより、今の女王がまだ候補生だった頃に抱いていた恋心とも全く違う、自分の存在そのものを根底から揺さぶるような、激しい恋に。
最初から、彼女の心にはオスカーの影があった。そして、誰の助けも借りずに自らそれを克服し、きりっと前を見据えて女王位を目指す彼女にこそ、彼は惹かれたのだ。
けれど、遠い高みへと飛び去ってゆこうとする彼女を、自分はそれでも追い求めていけるだろうか。いや、求めてもよいのだろうか。
女王と守護聖の恋自体は禁忌ではないし、彼女に好意を抱いてはもらえているとも思う。なにより彼女と離れたくなどはない。
だが、まっすぐに前だけを見つめて突き進む彼女に、自分のこの一方的な想いをぶつけていいものかどうか。
迷ううちに、今日まで来てしまった。残された時間はあとわずかだ。
……オスカー様も、かつてこんな思いを抱いたのだろうか。
この苦しさを、あの人はどのように昇華したのだろう。今、切実に、その心の強さが欲しい。
ふと、暖かな波動を感じて目を上げると、そこに金の髪の少女が立っていた。
女王の盛装ではなく、年相応のシンプルな白いワンピースに身を包み、にっこり笑いかけてくる彼女は、候補時代そのままの一人の少女にしか見えなかった。
「──やあ」
自ら仕える宇宙の女王に対して、不遜な呼び掛けをしているとは思ったが、今の彼女には普通の女の子として対するのが正しい気がした。だから、その感覚に従った。
アンジェリークはにこっと嬉しそうに笑って、彼の傍に歩み寄ってきた。
「こんばんは、ランディ」
「…こんな夜に、しかも一人で宮殿を抜け出してくるなんて、オスカー様に知れたらすごく怒られるぞ」
彼女を見上げながらくすりと笑ってそう言うと、アンジェリークはちょっと肩をすくめて、ランディの隣にちょんと腰を降ろした。
「聖地の中なら平気なのにね。だいたい、邪悪な気配があれば、私はすぐにわかるもん」
「そういう問題じゃないだろ?」
「オスカーもそう言うわ」
アンジェリークはくすくす笑って、それからまっすぐにランディの顔を覗き込んできた。
「風のサクリアに乱れを感じたわ。──苦しそうね、ランディ」
その声にいたわりの響きを感じ取って、ランディは慌てて顔をひきしめた。
「ごめん! 君を守り支えるべき俺が、君に心配かけちゃうなんて、最低だよな」
「ううん、いいの。──ね、ランディ? あなた、あの子を女王にしたくないと思う?」
すぱりといきなり核心を突かれて一瞬詰まり、ランディは苦笑しながら空を仰いだ。
「………そうだな」
女王陛下は、俺の気持ちもお見通しだったっていうわけだ。…ひょっとしたら、こういうことには敏いだろう恋人から聞いたものかも知れないけれど。
降るような満天の星を見上げて軽く息をつくと、彼はゆっくりとアンジェリークに視線を戻して答えた。
「いや。彼女は新宇宙にふさわしいし、新宇宙も彼女にふさわしいと、心からそう思うよ」
そう言いながら心の片隅で、いつか同じ言葉を目の前の少女を愛する人から聞いたことがあったなと思い、ランディはほろ苦い笑みに唇を歪めた。
あんなに堂々と、強い心で言い切れるわけではないけれど、それでも本当にそう思えるから。そう言えた自分を、少しだけ誇りに思う。
するとアンジェリークは緑の瞳に真剣な光を浮かべ、重ねて問いかけてきた。
「じゃ、あの子のこと、あきらめる?」
その張り詰めた表情を見た瞬間、ふっと迷いが晴れた心地がした。
ランディは彼女を安心させるようににこりと笑うと、背筋を伸ばして星空を見上げ、きっぱりと言った。
「あきらめないよ。彼女が女王になっても、例え別の宇宙に行ってしまっても、気持ちは変わらない。──いつか必ず、振り向かせてみせる」
そうだ。あの一途な瞳に自分をまっすぐ見つめて欲しい。
彼女が好きだ。
この強い気持ちの前には、立場も距離も何ほどのものだろう。
「それを聞きたかったの。安心したわ」
にこにこっと笑み崩れたアンジェリークが、いたずらっぽい光を浮かべてランディを見上げる。
「協力しちゃう。いつでもこっそり次元回廊開いてあげるからね!」
ぽんっと跳ねるように立ち上がった少女は、彼の目の前で嬉しそうにくるりと回り、それからくすくすと笑った。
「宇宙で一番強い味方よ、感謝してねランディ?」
どこか小悪魔っぽいその笑みに、思わずランディもつられて笑った。
肚が決まったというだけで、なんと心が軽くなることか。久々に晴れ晴れと笑って、ランディは立ち上がると女王陛下に正式の礼をした。
「感謝します。…今夜のことも。本当にありがとう──宮殿までお送りします、陛下」
「あ、その必要はないみたい。…ほら」
アンジェリークの視線を追って振り返ると、夜に溶け込むような黒衣に黒いマントをはおった炎の守護聖が、怖い顔でこちらを睨みながら足早に近付いてくるところだった。
「オスカー」
アンジェリークは嬉しそうに笑って、彼の方へと駆け寄った。
「やっぱりここだったか。──こんな夜に一人で抜け出すだなんて、何を考えてるんだ」
説教口調でつかつかと歩み寄るオスカーに、アンジェリークはうふふと笑って首をすくめた。
「大丈夫だって言ってるのに。それに、必要だと思ったから来たのよ」
「そりゃわかってるが、万一ということもあるだろう。…あまり心配させるな」
オスカーは低く呟くと、マントを外してふわりとアンジェリークの体に回しかけた。
「冷えるぞ」
「平気よ」
「いいから」
有無を言わさずアンジェリークをすっぽりと包み込んでしまい、それからオスカーはランディの方へすっとその強い視線を向けた。
彼は、言葉に出しては何も言わない。言う必要がないと思ってもらえているのだと、ランディにもわかっている。
だからランディも黙ったまま、しゃんと姿勢を正して一礼した。
オスカーは、フッと軽く笑って雄弁な一瞥を投げ返し、それからアンジェリークの華奢な肩を抱いて歩き出した。
黒衣の彼と黒いマントに包まれた少女のシルエットが、寄り添いながら夜闇に溶け消えていく。それを感慨深く見送ってから、ランディはもう一度夜空を見上げ、きゅっと口元をひきしめた。
それから彼はくるっと踵を返し、ゆっくりと走り出した。やがてそのスピードがぐんぐん上がってゆく。
心が決まった以上、明日まで待ってなどいられない。
今すぐに、会いに行こう。
そして告げよう。
誇り高く勝ち気な瞳の君が好きだと──風のように軽やかな、捉えがたく自由なその魂を、愛しているんだと。
例え遠く離れた宇宙の女王になってしまっても、君を、口説く。
君は、どんな顔をするだろう。
その海の色の大きな瞳を一杯に見開いて驚くだろうか。それとも────
女王候補寮の明かりが、見えてきた。
・◆ FIN ◆・
BACK ・◆・ HOME
|